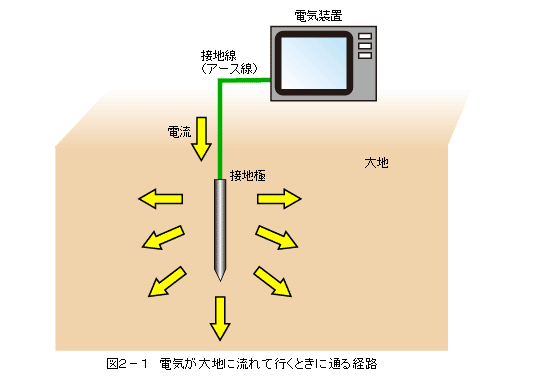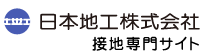2.接地抵抗
1)接地抵抗とは
『接地抵抗』という言葉は、『接地』と『抵抗』という2つの言葉から成り立っています。
- 接地(アース)…電気装置などを大地と接続すること。また、その接続線。
- 抵抗…外からの力に対し、張り合い逆らうこと。電気抵抗であれば、電気の通りにくさを示す値。
つまり、『接地抵抗』とは、“電気装置などを大地と接続した時に電気の通りにくさを示す値”という意味があります。
電気が大地に流れて行くときに通る経路は、図2−1のように、電気装置→接地線(アース線)→接地極→大地となっています。
接地線(アース線)や接地極の抵抗は、金属製のため問題となりません。また、接地極と大地との接触抵抗も工事の時にそれらが十分に密着するように配慮することで小さいものとなります。しかし、電流が最終的に流れ出て行く大地の持っている抵抗の性質を変えることは困難です。つまり、接地抵抗は“大地の持つ電気的な性質(大地抵抗率)”に大きく依存しているということになります。